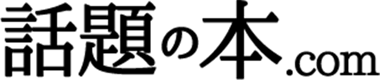ペットの寿命が延び、飼育環境や飼い主の意識も変化し、がんや関節疾患、生活習慣病などまるで人間の病院と同じような病気で受診するペットたちが増えてきた昨今。動物医療の業界でも新たな医療ニーズに対応すべく、高度医療・専門医療の動きが広がりつつあります。
そこで、本稿では動物の高度医療を担う獣医師が、診断や治療の最前線を紹介し、ペットの「こんなとき、どうする?」という悩みに症状別に解説していきます。
第1回目は高度・専門医療の実際―循環器科・心臓外科編をお届けします。ここでは「僧帽弁閉鎖不全症」「動脈管開存症」「肺動脈狭窄症」の3つの病気を挙げ、病気の概要や症状、診断・治療方法などを紹介していきます。
犬の心臓病の9割を占める「僧帽弁閉鎖不全症」
「僧帽弁閉鎖不全症」とは
僧帽弁閉鎖不全症とは、心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁という弁に異常が起こる病気です。
加齢やその他の理由によって弁がもろくなるなど性質が変わってしまうと、本当なら左心房から左心室に流れるはずの血流が、左心室から左心房へと逆流してしまいます。
血液が逆流すると、全身に送り出せる血液の量が減ってしまいます。初期の段階では飼い主が見ている範囲では異常は感じられませんが、病気が進むと、心不全などが起こりやすくなり、最終的には肺に悪影響が出て酸素濃度が低下し、命に関わるようになります。
僧帽弁閉鎖不全症は主に小型犬や中型犬に多い(特に高齢)心臓病で、大型犬ではあまり起こりません。犬の心臓病の9割を占めるといわれています。一方で猫にはこの病気はあまりみられません。
「僧帽弁閉鎖不全症」の症状
初期の症状は5〜6歳が最も多いと言われていますが、この段階ではあまり目立った症状は起こりません。
症状が進行してくると、散歩に行くのを嫌がったり、食欲が落ちる、呼吸をするときに苦しそうな様子をする、呼吸が苦しくて夜眠れないなど、目立った異変も増えてきます。
さらに進行すると、毛細血管から血液の液体部分が漏れ出して肺胞の中に溜まる状態である、肺水腫になります。ここまで進行すると、その後は1年ももたないともいわれています。
僧帽弁閉鎖不全症を早期発見するには、定期検診をしっかり受けて、そこで心臓の音を丁寧に聞いてもらうことが重要です。
「僧帽弁閉鎖不全症」の診断
問診や聴診器で雑音を確認したうえで、診察では心拍数や呼吸数などを計測します。同時に、血液検査なども実施し、特に心臓病ではANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)やBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)と呼ばれるホルモンの数値が重要視されます。
また、心電図検査で不整脈の有無などを確認したり、レントゲン検査などで、心臓の大きさや胸や腹に水が溜まっていないかどうか調べることも有効的です。より病気の状態を調べるには超音波検査が必要となります。
「僧帽弁閉鎖不全症」の治療
僧帽弁閉鎖不全症の治療方法は、病気の進行状況や犬の年齢、全身状況などを総合的にみて判断します。
症状が出始めて最初の頃であれば、投薬による内服治療を検討します。内服治療で用いられるのは、血管拡張薬や利尿剤、強心薬などで、これらの服用によって心臓の拡大化が抑制されたり、少しでも小さくなるなど総合的にみて症状が安定していけば、そのまま内服薬で様子をみることもあります。
以前は僧帽弁閉鎖不全症といえば、薬で症状を緩和したり、少しでも進行を遅くするのが主な治療法でしたが、今では手術で薬を飲まなくてよいレベルにすることが可能になってきています。
僧帽弁閉鎖不全症の手術は「僧帽弁形成術」と呼ばれ、人工心肺装置を使用し、広がってしまった僧帽弁を糸で縫い縮めたり、切れてしまった腱索を再建します。手術はトータルで5、6時間ほどかかりますが、万が一、出血などが起こった場合は時間もさらに長くかかります。
内科的治療と外科的治療のメリット・デメリット
内科的治療のメリット
・内服薬の治療なので手術ほどの極端な命のリスクはなく、ある程度の期間は生存が担保
内科的治療のデメリット
・病気は基本的に完治することはなく、少しずつ悪化
・薬で行える治療には限界があり、毎日、一生涯薬を飲ませ続けることの手間やコストが発生
外科的治療のメリット
・手術さえ乗り切ることができれば、かなり良い状態まで改善を望める
・手術が成功すれば、基本的に薬の服用はまったくいらない
外科的治療のデメリット
・一定のリスクがつきまとう
・万が一、手術がうまく行かなかった時は死んでしまう可能性がある
・手術自体は成功しても、合併症によって亡くなることもある
手術が適しているのか内服薬で様子をみるべきかは、年齢や症状、進行具合、全身状態などをトータルで考えて判断する必要があります。納得のいくまで主治医と話し合うことが大切です。
猫よりも犬に多い「動脈管開存症」
「動脈管開存症」とは
本来であれば生まれた後に自然に閉鎖するはずの動脈管という管が、閉鎖せずにそのまま残ってしまう病気です。動脈管が残っていると、全身を巡るはずの血液の一部が大動脈から肺動脈に流れたり、反対に肺動脈から大動脈に流れるなど、血液に異常が生じてさまざまな症状が起こってしまいます。
猫よりも犬に多く、特にトイプードルやミニチュア・ダックスフンド、マルチーズ、ポメラニアンなどの小型犬に多い傾向が知られています。また、犬ではオスよりもメスに多い傾向があります。
「動脈管開存症」の症状
初期には症状がないこともありますが、症状が進んでくると咳が出たり疲れやすかったり、呼吸が苦しそうだったりする症状が現れます。
さらに進むと、全身の酸素が不足することによって、皮膚や粘膜が変色するチアノーゼという症状やお腹に水が溜まる腹水などが起こることもあります。
「動脈管開存症」の診断
まず聴診器で心音を聞き、特徴的な心雑音が聞こえるか確認します。次いで、レントゲン検査や血液検査を実施し、心臓の拡大や肺動脈などの拡大を確認します。さらに詳細に調べるには、超音波検査などを行い、動脈管が残っているかどうかや血液の異常の有無、合併症などをしっかりと調べます。
「動脈管開存症」の治療
動脈管開存症は、胸を開く開胸手術やカテーテルという細長い管を使った手術などの外科的手術によって治すことができます。胸を開いて手術するよりも、カテーテルにより治療のほうがリスクが少なく、その後の回復が早いというメリットがあり、胸を開いて行う手術では、術後数日間~1週間程度は傷の痛みなどが残りますが、カテーテルを使った治療であれば、手術の翌日には元気に退院できることもあります。
進行すると心不全などを引き起こす「肺動脈狭窄症」
「肺動脈狭窄症」とは
肺動脈が狭くなることで起こる心臓病です。先天性の心臓病のなかでは、比較的多くみられる病気の一つです。肺動脈の弁が狭くなることによって血液が流れにくくなると、右心室に負担がかかります。この状態が長く続くと心不全などの重大な症状を引き起こします。
「肺動脈狭窄症」の症状
初期では症状がみられないケースが大半ですが、進行すると咳が出たり、呼吸が速くなる、少し運動しただけで動きたがらないなどの症状が出ます。重度の場合は突然、意識を失って失神することもあり、脈が不規則な状態になる不整脈を発症したり、心不全が進行すると胸や腹に水が溜まって肺水腫を引き起こすこともあります。
「肺動脈狭窄症」の診断
問診などに加え、聴診器で心雑音を確認、このほか血液検査やレントゲン検査、超音波検査などを実施します。超音波検査では肺動脈の弁がどのようになっているか、どの程度狭くなっているのか、あるいは肺動脈が拡大していないかなどを調べます。
「肺動脈狭窄症」の治療
軽度の場合は、特に治療をしなくてもよいケースもあります。症状が進行している場合は、主にバルーンを使ったカテーテル治療など外科的手術を検討します。そのほか胸を開いて器具を挿入し、直接肺動脈弁を拡張させる治療法や薬を中心とした内科的治療もあります。
<循環器科 獣医師 井口和人先生>

飼い主のペットに対する健康志向が高まるにつれて、動物医療に対して求められることは多様化し、専門的な知識が必要とされてきています。
内科、外科、耳鼻科、眼科……と細かく診療科が分かれている人間の病院に対し、動物病院は多くの場合、1人の医師が全身すべての病気を診る「1人総合病院」状態が一般的でした。
しかし、そこから脱却し、高度医療を担う施設や専門分野に特化した病院の増加、施設間で連携し紹介しあう体制づくりなど、人間のような医療体制が求められています。
動物にも高度で専門的な知識を提供できれば、今まで救えなかった命を救うことができるからです。
本書では、グループ病院全体で年間3000件を超える手術を行うなど、動物の高度医療を目指す獣医師が、診断や治療の最前線を紹介し、ペットの「こんなとき、どうする?」という悩みにも、症状別に分かりやすく解説しています。