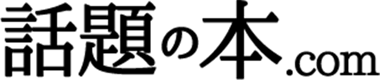ペットの寿命が延び、飼育環境や飼い主の意識も変化し、がんや関節疾患、生活習慣病などまるで人間の病院と同じような病気で受診するペットたちが増えてきた昨今。動物医療の業界でも新たな医療ニーズに対応すべく、高度医療・専門医療の動きが広がりつつあります。
そこで、本稿では動物の高度医療を担う獣医師が、診断や治療の最前線を紹介し、ペットの「こんなとき、どうする?」という悩みに症状別に解説していきます。
第3回目は高度・専門医療の実際―脳神経科・リハビリテーション科編をお届けします。ここでは「てんかん」「脳腫瘍」「水頭症」「認知症」「椎間板ヘルニア」の5つの病気を挙げ、病気の概要や症状、診断・治療方法などを紹介していきます。
脳の代表的な疾患「てんかん」
「てんかん」とは
脳の特定の部位で、興奮と抑制のバランスが崩れてしまい、大脳から電気的な信号が過剰に送り続けられ、興奮状態に陥ってしまうてんかん発作が繰り返し起こる病気です。犬猫でてんかんを発症する割合は、1~5%といわれ、100匹いれば5匹程度がてんかんをもっている可能性があります。
脳に器質的異常が見られないものを「特発性てんかん」、脳腫瘍や脳炎など大脳の病気が原因となるものを「構造的てんかん」などと呼びます。
「てんかん」の症状
最も多い症状はけいれんで、全身がけいれんして意識を失ってしまうようなケースもあれば、顔の一部だけがピクピクとひきつっていつなど、体のごく一部にだけけいれんが起こるケースまでさまざまです。
けいれんのほかの症状には、発作的に発狂したようになったり、「フライバイト」と呼ばれる何もない空中を見つめてハエなどの小さな虫を噛むような動作や、追いかけるような動作をする症状もあります。
てんかんは慢性的な病気であるため、発作も繰り返し起こるのが特徴です。神経系の病気の特徴として「突然起こることがある」が挙げられます。「5分以上続くけいれん発作」や「1日に5回以上の頻度でけいれん発作」が起こる場合はなるべくすぐに受診したほうがよいと思います。
「てんかん」の診断
診断は大きく3段階に分けることができます。
第1段階は、飼い主への問診とペットの観察からスタートします。次の神経学的検査では、「ハンドオフ」(手を使わない観察)と「ハンドオン」(体を触って行う)の検査を行います。ほかには、血液、尿、レントゲン、超音波、血圧などの一般的な検査を実施し、発作を起こす可能性のある脳以外の疾患がないかを確認します。
第2段階としてMRI検査や脳脊髄液検査などを行い、脳に異常があるかどうかを調べます。これにより、脳に疾患があり起きている発作なのか、疾患がなくて起きている発作なのかを分類できます。この段階で脳の病気が原因で発作が起きていると判明した場合は、発作を抑える治療の他に、発作の原因になっている炎症や腫瘍に対する治療が必要になります。脳に異常が見つからない場合は、特発性てんかんである可能性が高まります。
第3段階は脳波測定です。脳波検査は、頭部に小さな電極の針や皿を設置し、電極と脳波計を接続して脳波を計測・記録します。MRIなどによってほかに脳の病気がなく、脳波検査でこのような異常が見つかった場合は、特発性てんかんであると診断をつけることができます。
「てんかん」の治療
てんかんは完治を目指す病気ではなく、症状をコントロールして生活にできるだけ影響が出ないようにしていくことが治療の主な狙いです。特発性てんかんの診断がついたら、治療は、抗てんかん薬を服用する薬物療法がメインになります。その他、補助的な治療として、サプリメントなどを活用することもあります。
このほか、てんかんの最新治療として、手術でてんかんを治療しようという取り組みも進んでいます。「難治性てんかん」に対して、発作の頻度や重症度を減らすことを目的に手術を実施しています。
高齢化に伴って増加する「脳腫瘍」
「脳腫瘍」とは
広くは頭蓋内に発生する腫瘍のことで、初めはてんかん発作や運動機能の障害などで飼い主が異変に気づき、そこから脳の病気の検査を進めていくなかで発見されるケースが多くなっています。最初にできた腫瘍が脳からである場合を「原発性脳腫瘍」と呼び、他の部位でできた腫瘍が脳に転移してきた場合を「転移性脳腫瘍」を呼びます。
脳腫瘍は犬や猫が高齢になるにしたがってかかりやすい病気で、ペットの高齢化に伴って、脳腫瘍を発生するケースが増えてきています。
「脳腫瘍」の症状
特に多い症状は発作です。ほかにもグルグルと一定の方向に向かって意味もなく歩く、ボーっとしていて飼い主が呼びかけても応答しない、姿勢や体のバランスが保てない、黒目が正面を向いていない、足に麻痺が起こるなどさまざまな症状が出現します。
「脳腫瘍」の診断
飼い主の問診とペットの観察に加えて、血液検査やレントゲンなど一般的な検査を行います。一般的な検査で分かる範囲に脳以外の病気がない場合は、脳や脊髄などの病気の可能性を疑い、MRI検査を行います。
「脳腫瘍」の治療
手術が出来る場合は手術で腫瘍を取り除くのがベストです。あるいは、腫瘍の種類によっては、抗がん剤治療を行うこともあります。そのほかには、放射線治療があります。外科的手術や抗がん剤治療、放射線治療などがいずれも難しいケースでは、対症療法によって苦痛を取り除く治療法を選択することもあります。
小型犬に多く、子犬の頃から異変が起きる「水頭症」
「水頭症」とは
脳内の脳室と呼ばれる空間に、脳脊髄液が溜まることで起こる病気です。猫が発症するケースはあまりなく、犬、特に小型犬に多い病気ですが、水頭症が遺伝性疾患であることが知られ、交配されなくなっているので近年は犬の水頭症も減少傾向にあります。
「水頭症」の症状
子犬の頃から出ることが多いのが特徴で、感情のコントロールができなかったり、発狂したように騒ぐ、あるいはやたらと攻撃的になるなども症状の一つとして現れます。また、てんかん発作や旋回運動、認知症と似たような症状、斜視、視力の障害、運動障害が起こる場合もあります。
「水頭症」の診断と治療
超音波検査やMRIによって脳室が拡大しているか、どの程度脳に圧がかかっているかを確認します。治療には、一般的にはステロイド剤などを投与することによって脳圧をコントロールする内科的な治療と、脳内にチューブのようなものを設置して、そのチューブを体の中に通して、腹腔内に流し込む外科的な治療があります。
早ければ11歳頃から発症するケースも…高齢化で増加する「認知症」
「認知症」とは
脳の病気や障害の影響、老化によって脳細胞の働きが衰え、認知機能が低下することで、さまざまな問題行動を起こします。ペットの寿命が延びるのに伴い、犬の認知症も増えています。
「認知症」の症状
いくらご飯を食べてもずっとお腹がすいたような様子をしている、昼夜逆転してしまう、目的もなくただただうろうろと歩いている、ひたすら吠え続けて止まらないなどがあります。
「認知症」の診断と治療
認知症のチェックリストに沿って点数化し診断します。このほかMRIなどによって脳の萎縮を確認します。認知症の場合は根本的に治すのは困難のため、なるべく進行を遅らせることを目的とした対処が行われます。薬物療法やサプリメントなどを使用した栄養療法、生活の改善、リハビリテーションなど行います。
ダックスフンドやコーギー、ビーグルがかかりやすい「椎間板ヘルニア」
「椎間板ヘルニア」とは
背骨の間にある椎間板という組織の一部が飛び出してしまい、脊髄神経を圧迫してしまう病気です。
「椎間板ヘルニア」の症状
最もよく見られる症状は麻痺で、ヘルニアの症状が軽いときは、麻痺まで至らずに痛みだけが生じるころもあり、抱き上げたり触ったりしたときなどに「キャン!」と大きな鳴き声をあげて痛がったり、怒ったりします。
「椎間板ヘルニア」の診断と治療法
まずは問診や触診を行い、実態に痛みが出ている個所や麻痺の有無を確認し、神経学的検査を行います。また必要に応じてMRIなどの画像診断を行います。
治療法は重症度によって変わり、痛みだけで麻痺がないケースでは、痛み止めの内服薬を使用、麻痺まで出ていたり、痛みを繰り返したりするケースでは手術が適応になります。
術後早期に始めることで効果が高くなる、リハビリテーション
手術をしたあと、運動機能を回復するためにはリハビリテーションが非常に効果的です。リハビリテーションの方法にはいくつかの方法があり、水中トレッドミルという装置を活用した水中療法や、神経機能を回復させるために障害物を意識しながら行う歩行訓練、道具を使ったリハビリテーションなどがあります。
一般的にリハビリテーションは手術後、適切な管理をしたうえで早期に始めることで効果が高くなると考えられているので、できるだけ早期にスタートするとよいでしょう。
<脳神経科 獣医師 大竹大賀先生>
<リハビリテーション担当 動物看護師 矢ケ崎望さん>

飼い主のペットに対する健康志向が高まるにつれて、動物医療に対して求められることは多様化し、専門的な知識が必要とされてきています。
内科、外科、耳鼻科、眼科……と細かく診療科が分かれている人間の病院に対し、動物病院は多くの場合、1人の医師が全身すべての病気を診る「1人総合病院」状態が一般的でした。
しかし、そこから脱却し、高度医療を担う施設や専門分野に特化した病院の増加、施設間で連携し紹介しあう体制づくりなど、人間のような医療体制が求められています。
動物にも高度で専門的な知識を提供できれば、今まで救えなかった命を救うことができるからです。
本書では、グループ病院全体で年間3000件を超える手術を行うなど、動物の高度医療を目指す獣医師が、診断や治療の最前線を紹介し、ペットの「こんなとき、どうする?」という悩みにも、症状別に分かりやすく解説しています。